- 医療関係者向けホーム
- 医療関連情報
- クリニック訪問記
- クリニック訪問記 vol.5 医療法人円山公園メンタルクリニック
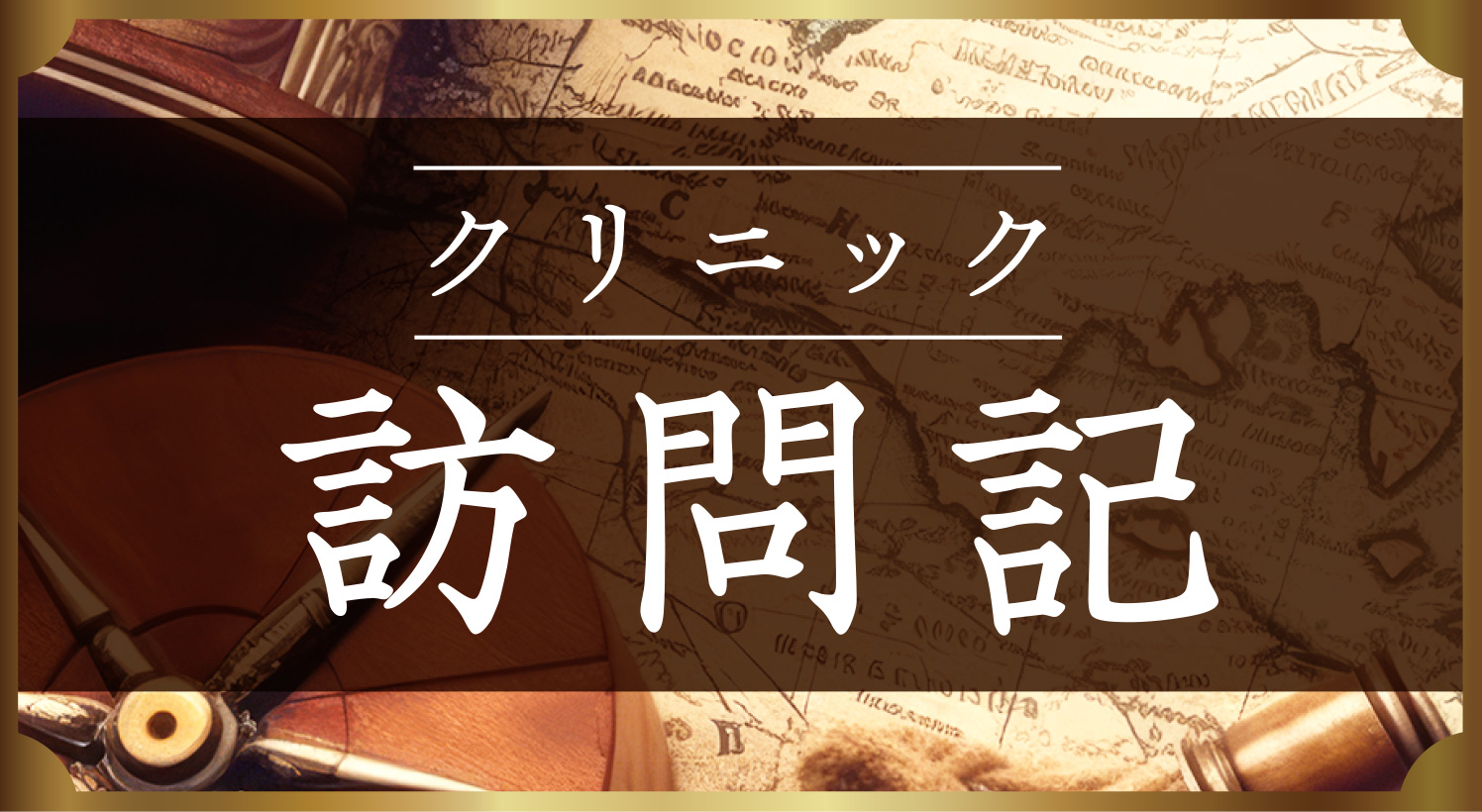
2024年05月14日公開

札幌市中央区にある円山公園メンタルクリニックは、2009年の開業以来「どのような精神疾患の患者さんでも可能な限り診る」ことをモットーに、地域密着型で幅広い世代の患者さんの診療をおこなっています。中高生や障がいを有する患者さんも多く来院されるという円山公園メンタルクリニックには、院長の白木淳子先生の考えや想い、様々なご経験から、患者さんが来院しやすい工夫が凝らされています。
今回、白木淳子先生には開業の背景やクリニックの特徴、地域の精神科医療機関としての取り組み、今後の展望などについてお話を伺いました。
施設紹介
■ 医療法人円山公園メンタルクリニック
北海道札幌市中央区大通西25丁目1-2
ハートランド円山ビル 3階
白木 淳子 先生
(医療法人円山公園メンタルクリニック 院長)

多くの経験を礎に、
精神科クリニックのなかった円山公園周辺地域で開業

白木淳子先生
(円山公園メンタルクリニック 院長)
父が精神科医ということもあり、私にとって「精神科」は幼い頃から馴染みがあるものでした。何となく「医師になった方がいいのかな」と思った時期もあったのですが、医師になるように親から勧められたことはなく、高校時代は化学の先生になりたいと考えていました。しかしながら、家族に重症心身障がい者がおり、生涯にわたり支援するためには医療を仕事とすることがよいと考え、医師の道を目指しました。
医師になってからは、研修先の病院で統合失調症をはじめとする様々な精神疾患の患者さんを診療してきました。加えて、障がい者施設や刑務所などの複雑な環境におかれた患者さんを診療する機会もあり、多くの経験を積むことができました。
精神科の医師として多くの患者さんの診療をしている中、恩師からの勧めや趣味として参加しているワイン好きの集まりで開業コンサルタントと出会ったことをきっかけに、当時は精神科クリニックが一軒もなかった札幌の円山公園周辺地域に開業しました。
中高生や障がいを有する患者さんが多いのが特徴
円山公園周辺地域は、文化施設や教育施設が集まった「文教地区」という土地柄からか、当院を受診される患者さんには進学校に通っている中高生が多くいます。これは勉強の詰め込みによるストレスだけでなく、親の過剰な期待に応えようと頑張り過ぎていることも原因ではないかと考えています。
また札幌市では、子どものこころの状態に合った適切な医療機関を紹介する「さっぽろ子どものこころのコンシェルジュ事業」をおこなっており、コンシェルジュ事業からの紹介で来院される中高生やその親御さんも多く見受けられます。
加えて、養護学校の卒業生や発達障がい・知的障がいといった、多くの障がい者の患者さんに受診いただいているのが当院の特徴です。その背景としては、私の家族には知的障がい者がおりますし、日曜学校や養護学校に通っている障がい者の方々と親しくさせていただいた経験から、障がい者の悩みやご家族の気持ちは身をもって理解していること、公的機関を経由して障がいを持つ患者さんやご家族に当院がおすすめされていること、あるいは障がい者のご家族の間で当院の評判が口コミで広がっていることなどが挙げられます。
コンセプトは「病院っぽくない」「温かみのある」空間づくり
患者さんにとって病院は、非日常で緊張する場所だと思います。仕事を終えてからいらっしゃる患者さん、学校帰りに通院される患者さんなど、様々な患者さんが「ここなら何となくほっとできるかな」と思える、カフェのような空間づくりを意識しています。木材の色味を活かした温もりを感じる床や、においや吸湿性を考え珪藻土を塗った壁など、病院っぽさをなくすだけでなく、クリニックとして長く続けていくにつれ味が出てくるようなデザインを取り入れました。ほかにも受付カウンターや待合室も円形にして角を作らないよう、できるだけ温かみを帯びた丸みのあるデザインにしました。以前に病院で勤務していた頃、待合室で患者さんが向かい合って座っていることに違和感があったので、円形にすることで患者さんがそれぞれ違う方向を向いて顔を見合わせずにすむ空間を創りだすことができました。

カフェのような空間を意識した待合室と
円形で温かみのある受付カウンター

患者さん同士が顔を見合わせずにすむ
カウンターテーブル
常勤のケースワーカーが患者さんの支援に活躍
当院では医師や看護師、受付スタッフ、臨床心理士のほか、ケースワーカーが常勤で在籍しています。デイケアをおこなっていないクリニックでケースワーカーが常勤していることは珍しいと思いますが、患者さんをきちんとサポートするため、また医師や看護師の負担を軽減するためにケースワーカーが活躍しています。たとえば障害年金や自立支援医療といった公的制度について患者さんへ説明するには専門知識が必要ですし、医師や看護師がおこなっていては本来の業務が滞ってしまうおそれがあります。そこでケースワーカーが専門的な知識と経験をもとに患者さんに説明し、ときには公的制度の利用申請手続きまでフォローすることで、手厚く患者さんをサポートできます。私自身もケースワーカーに安心して任せており、それは当院の大きな特徴だと思います。
スタッフ全員で取り組む、
電子カルテを活用した情報共有とコミュニケーション
スタッフ間の情報共有やコミュニケーションには、電子カルテの機能を活用しています。
たとえばお話を聞くのに時間がかかる患者さんは、電子カルテにその旨のマークを付けておきます。その患者さんが次回受診された際は、診察前に看護師やケースワーカーがお話を伺って、その内容を電子カルテに記載します。私は電子カルテの記載内容を確認したうえで診察しますので、役割分担と効率化を図ることができます。また患者さんは、医師である私には話しづらいことを看護師やケースワーカー、受付など、ほかのスタッフに話すことがあります。そうした情報も診療上貴重なので、電子カルテに記載して情報共有するようにしています。
スタッフ間のコミュニケーションには、電子カルテのメッセージ送信機能が大いに役立っています。診療時間中、私は診察室からなかなか出ることができませんし、ときには患者さんに聞かれては困るようなやりとりをスタッフ間でする必要があります。たとえば待合室にいる患者さんの咳が診察室まで聞こえてきたときは、私が「咳をしている患者さんがいるようだけど、大丈夫?」とメッセージを送り、スタッフと対応の仕方を相談します。逆に受付から「イライラして待合室でウロウロしている患者さんがいます」と私にメッセージが送られてきたら、早めに診察するなど適切な対応をとることができます。
こうした情報共有やコミュニケーションは、患者さんを待たせず安心して診察を受けていただくことにつながるので、スタッフ全員で協力して取り組んでいます。
地域の先生方と関係を構築するため、
地域の医師会などの役員を務めイベントにも参加
私は「クリニック」は病院とは違い、気軽に来ていただける「よろず相談所」のような場所だと思っています。ですから、当院では基本的にどのような精神疾患の患者さんでも断らずに診療しています。精神科クリニックの医師として、できるだけ患者さんを入院させずクリニックで診療したいのですが、どうしても難しい場合があります。そこで地域の先生方との関係を構築するために、地域の医師会や精神科診療所協会の役員を務め、医師会主催のイベントにも積極的に参加するようにしています。また当院が入っているメディカルモールには11ものクリニックが入っており、他科の医師との連携がしっかりできているので、患者さんにも安心して受診してもらいやすいのではないかと思います。
患者さんとの信頼関係が治療をスムーズに行うために大切
治療にあたって重視しているのは、患者さんとの信頼関係です。信頼関係を築くために、初診の段階で患者さんの悩みや困っていることをしっかりと傾聴し、また診断結果や治療の方針、想定される治療経過などについて十分に説明します。たとえば抗うつ薬のように漸増投与する薬剤の場合、治療開始時に患者さんに「少しずつ用量を増やすお薬です」と説明しておかないと、増量したときに「具合が悪くなっているのかもしれない」と誤解や不安を招くおそれがあります。
患者さんとの信頼関係を構築できれば、その後の治療をスムーズに進めやすいですし、治療を成功に導くためにも大切なポイントだと思います。
今後
の
展望
患者さんの安心のためにも、
できるだけ長く当院で診療を続けたい
2009年の開業以降、様々な先生方に出会っていろいろ教わり、助けていただきながら診療してきました。
円山公園周辺地域のメンタルケアのためにも、私はできるだけ長く精神科医として当院で診療を続けたいと考えています。同じ医師が長年にわたって患者さんに寄り添い続けることが「クリニック」の大きな役割ですし、患者さんにも安心して受診し続けていただけるのではないかと思います。
そして将来、私が引退した後も「円山公園メンタルクリニックに来れば安心」と患者さんに思っていただけるようなクリニックに育てていきたいと思います。

