- 医療関係者向けホーム
- 医療関連情報
- クリニック訪問記
- クリニック訪問記 vol.10 医療法人社団つたの葉 古新町こころの診療所
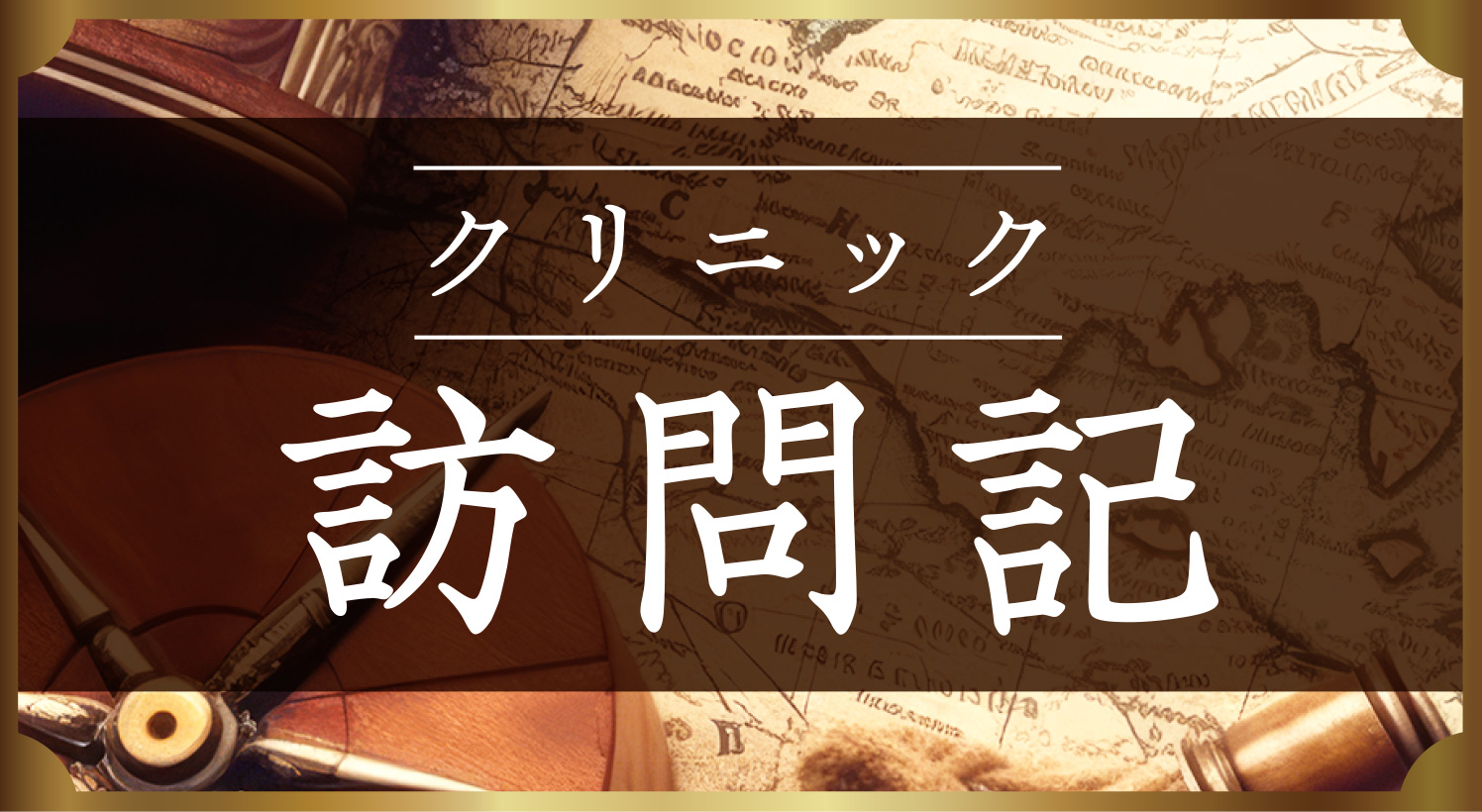
2025年08月26日公開
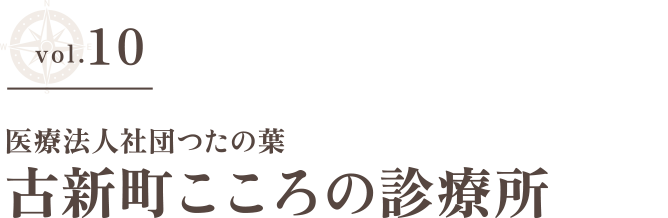
香川県高松市の中心部にある古新町こころの診療所は、「誰もが気軽に受診できる居心地のよいクリニック」を目指し、患者さんが安心して受診できるよう細部に至るまで配慮がなされています。院長の朝日宏美先生は、大学病院で長年培ってきた豊富な経験を活かし、大人の発達障がい(神経発達症)や摂食障がい(摂食症)、思春期のこころの悩みを中心に診療を行っています。今回は、患者さんとのコミュニケーションを大切にした診療を信条としている朝日宏美先生に、開院の背景やクリニックの特徴とこだわり、精神科診療の考え方、今後の展望などについてお話を伺いました。
施設紹介
■ 医療法人社団つたの葉 古新町こころの診療所
香川県高松市古新町10-3
砂屋ビル6F
朝日 宏美 先生
(医療法人社団つたの葉 古新町こころの診療所 院長)
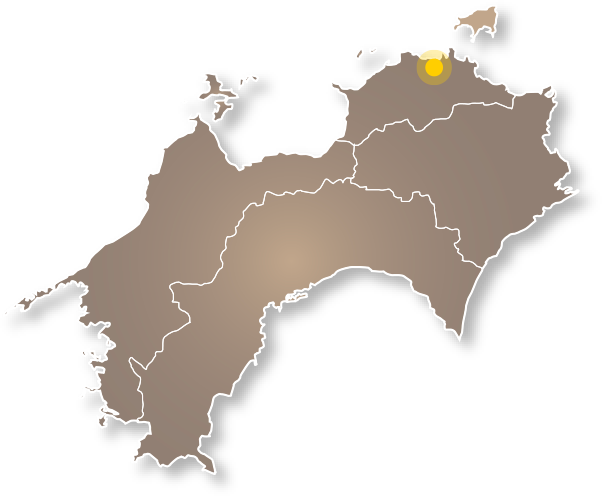
一人の患者さんと長くじっくり関わりたいという思いから、
精神科を選択

朝日 宏美 先生
(古新町こころの診療所 院長)
私は、両親とも医師という家庭に生まれ育ちました。高校生の頃、両親への反抗心から「医師だけにはなりたくない」と思ったこともありましたが、幼少期から両親の仕事の話を聞いて育ったためか、医師以外の職業で働く自分自身の姿を想像できなかったことから、地元の香川医科大学(現・香川大学医学部)に進学しました。
精神科を選んだ理由は、「患者さんと時間をかけてしっかり関わっていきたい」という思いからでした。多くの精神疾患は治療に時間がかかります。だからこそ、患者さん一人ひとりに対して最後まで責任を持って向き合うことができる、精神科はそんな診療科だと考えたからです。大学院卒業後は、主に大学病院に勤めて様々な臨床経験を積みましたが、当時から医師として働き続ける上で、自分のクリニックを開業したいという考えを持っていました。また、大学病院では比較的重症な患者さんを診療していたのですが、もっと気軽に受診できて、もっと早い段階で治療的介入ができるようなクリニックを作りたいと思うようになり、2016年4月に「古新町こころの診療所」を開業しました。
患者さんが受診しやすくて
リラックスできる空間づくりを徹底
当院のコンセプトは「誰もが気軽に受診できる居心地のよいクリニック」です。大学病院に勤めていた頃は「病院に来るだけで疲れる」「元気が出ないと病院に来ることができない」といった患者さんの声をときどき耳にしました。元気になってもらうために病院へ来てもらうはずが、これでは本末転倒だと思います。そこで開業する際に、患者さんが受診しやすくリラックスできる、よい意味で病院らしくない雰囲気のクリニックを目指しました。床は木目調にし、インテリアもナチュラルで温もりの感じられるものを採用し、おしゃれなカフェのような空間となっています。
院内は入口でスリッパに履き替えていただきますが、これも靴を脱ぐことでリラックスした状態で受診できるようにするためです。他にも医師が白衣を着ると患者さんに威圧感を与えるのではないかという考えから、私は白衣を着用せずに診療しています。また、面談室に「そら」や「うみ」といった名前を付けることで、患者さんを部屋にお呼びする際も病院っぽさを感じないような工夫をしています。
最近、当院ではインスタグラムを活用した情報発信を行っています。インスタグラムには、私が様々なことについてお話しする動画や、院内写真などを掲載しており、どんな医師なのか、どんなクリニックなのかを知っていただくことができます。これもまた、患者さんが受診するハードルを下げるのに貢献しているのではないかと考えています。

待合室。おしゃれなカフェのような空間で
患者さんにリラックスしてもらえる。

面談室入口。面談室は「そら」「うみ」と名付けられ、
病院っぽさを軽減。
大人の発達障がいを中心に、
若い世代の患者さんのこころの悩みをサポート
私の専門領域は、大人の発達障がいや摂食障がい、思春期のこころの悩みです。特に、大人の発達障がいについては、近隣で診療しているクリニックがまだ少ないためか、他院からの紹介を含め多くの患者さんが来院されます。また、思春期の患者さんも多く、学校が終わってから自転車で通院されている方もいらっしゃいます。
一方、摂食障がいの患者さんはそれほど多くなく、ご自身やご家族が熱心に病気やクリニックについて調べた上で来院されます。発達障がいは比較的疾患に対する啓発が進んでいるので、患者さんが直接来院されたり他院から紹介されたりといった流れが比較的できているのですが、摂食障がいは疾患啓発がまだ進んでいないため、患者さんやご家族が自力で対応するしかないという状況なのかもしれません。
なお、当院では認知症は診療しておらず、他院へ紹介し専門医に診ていただくようにしています。
多職種によるチーム医療で患者さんをサポート
一人でも多くの患者さんに対応できるよう、またできるだけ丁寧に患者さんのお話を聞けるよう、医師1名、看護師2名、公認心理師、精神保健福祉士が各1名、受付2名(2024年10月現在)が多職種チームとなって患者さんをサポートしています。診療前の問診は看護師が、カウンセリングは公認心理師が、社会復帰などの相談は精神保健福祉士が担当するというように、各々の職種が与えられた役割をしっかり果たすことで、患者さんの満足度が下がらないような工夫をしています。
また、当院は完全予約制のため、毎朝全スタッフでミーティングを行い、来院予定の患者さんについて情報共有しています。ここ最近の状態があまりよくない患者さんや、薬剤を変更したばかりの患者さんなど、それそれの患者さんで注意すべき点をスタッフ全員であらかじめ確認することで、トラブルの予防にもつながっているのではないかと思います。
的確な心理検査を実施し、
『目に見える』メンタルヘルス治療を提供
精神疾患は客観的なバイオマーカーが存在しないため、評価がとても曖昧です。当院では、公認心理師による心理検査を積極的に取り入れて患者さんの状態を「見える化」し、一人ひとりの状態に適した治療と支援につなげるようにしています。例えば、抑うつ症状で受診した患者さんが、「この程度の悩みで病院に来てよいのだろうか」とか「単なる甘えではないだろうか」など大した症状ではないと考えていたとしても、実際に心理検査をしてみると重症のうつ病という結果が得られることがあります。このようなケースでは、患者さん自身も「実は無理をしていたんだな」と気づくことができます。また、患者さん自身が症状の改善を感じて復職したいと思っても、心理検査の結果、改善が不十分であれば復職できません。そのような場合、心理検査の結果をもとに復職できる状態ではないことを患者さんに説明することもできます。
患者さんに寄り添ったコミュニケーションをとり、
よき理解者として解決策を探す
患者さんと接する際には、患者さんに寄り添ったコミュニケーションを大切にしています。初診の患者さんやまだ受診回数の少ない患者さんには「ここに来るまで、つらくなかったですか?」とお声がけをして患者さんの努力を労います。また、なかなか復職できない方に対しても、復職できない原因を知りたいという純粋な気持ちで接して患者さんのよき理解者として一緒に解決策を探していくことが大事だと考えます。
薬物療法と非薬物療法を
適切に用いながら症状の改善を目指す
患者さんから「薬剤を使わずにカウンセリングだけで治療してほしい」という要望をいただくことがあります。しかし、重症度が比較的高い方を非薬物療法だけで治療するのは、患者さんにとってもスタッフにとっても好ましくありません。医師がきちんと患者さんの重症度を判断し、それに見合った治療を選択することが大切で、そのためにも心理検査の結果は非常に重要です。もし、カウンセリングによる治療を希望されても、薬物療法が必要と判断される場合には、その旨をきちんとお伝えします。
薬物療法を行う際は、ガイドラインおよび薬剤の添付文書に沿って、適切な薬剤を十分量十分期間使用することが大切です。また、薬物療法について患者さんへ説明する際は、どういう薬剤を使うのか、漸増する薬剤では少量から投与を開始すること、どのような副作用が生じる可能性があるのか、生じた場合はどのような対応をするのかなど、丁寧な説明を心がけています。副作用の説明ばかりでは患者さんが心配になってしまうので、抗うつ薬の場合は「すぐにはよくならないけれども、徐々に症状が改善して思い詰めることが少なくなっていきますよ」という風に、効果についてもきちんと説明しています。これにより、患者さんが薬物療法を受けたあとの自分の変化をイメージしやすくなり、治療中も自分がどのような回復過程にあるのかを理解しやすくなると思います。
リワークプログラムで、
復職後も安定した就労が継続できるよう支援
当院では、集団精神療法や認知行動療法を取り入れたリワークプログラムに注力しています。
リワークプログラムでは患者さんの生活リズムを整え、仕事でつらかった点を振り返るなどの自己分析をします。このとき集団精神療法を取り入れることによって、同じ「復職」という目標を持った患者さんが集まって、それぞれの悩みを共有し合うことで「みんな同じような悩みを持っているんだ」と、孤独感を緩和することに役立ちます。また、それぞれの悩みについてお互いに意見を出し合ったりサポートし合ったりできるのも、集団精神療法のよさだと思います。
また、リワークプログラムでは復職後に生じ得る「ストレス」への対処法を身につけることも重要です。そこで認知行動療法を取り入れ、仕事で嫌なことがあったときの受け止め方や、自分が困っているときの相手への伝え方などについて、週3回、3ヵ月間のアサーション・トレーニングで習得してもらいます。
摂食障がいの家族会を開催し、
互いに支え合う場を提供
当院では、摂食障がいの家族会も開催しています。家族会を始めたきっかけは、摂食障がいの患者さんをどのようにサポートしたらよいか悩まれているご家族が多い一方で、そのことについて診療時間内で十分にお伝えすることが難しいためです。最初に、摂食障がい患者さんへの対応について、私からご家族へ向けて講義を行い、その後、講義に関する感想やそれぞれの近況などをご家族同士で自由に話し合ってもらいます。当院の2名の看護師は大学病院で摂食障がいの患者さんやご家族のサポートに携わっていたので、家族会の運営は看護師が積極的に取り組んでくれています。
今後
の
展望
公認心理師の育成とオンライン診療の導入で
精神科診療をよりよいものに
今後の目標は2つあり、1つは公認心理師を育成することです。公認心理師という国家資格ができたものの、実際の医療現場においてしっかり働ける人材をどのように育成するのかは、今後の課題だと考えています。当院でも研修生を受け入れられるように申請し、資格取得のお手伝いができればと考えています。さらに、若手の公認心理師を積極的に採用して、臨床場面でのカウンセリング経験を積んでもらうようにしたいと考えています。
もう1つはオンライン診療の導入です。オンライン診療は患者さんの通院の負担軽減や受診ハードルを下げることができるといったメリットがあるので、瀬戸内海の島々の患者さんや遠方の患者さんを今まで以上にしっかりサポートできるようになると思います。
いずれも高い壁を乗り越えなくてはいけませんが、よりよい精神科医療の実現のために精一杯取り組んでいきたいと思います。

