- 医療関係者向けホーム
- 医療関連情報
- クリニック訪問記
- クリニック訪問記vol.8 医療法人 西江こころのクリニック
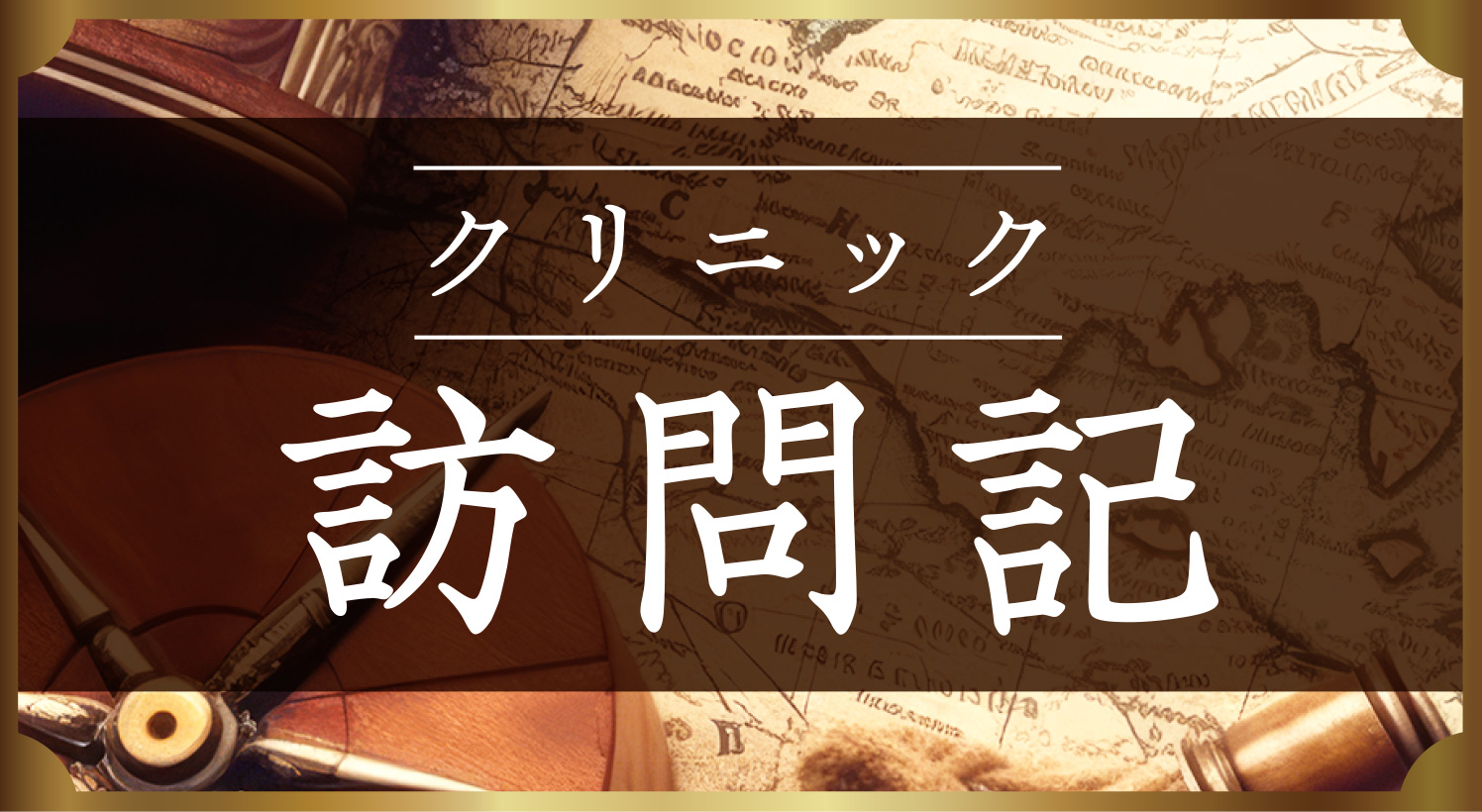
2025年04月22日公開

福岡県春日市にある西江こころのクリニックは、家族で受診できるクリニックとして幅広い年代の患者さんを受け入れています。また同クリニックは、認知行動療法/カウンセリングや訪問看護、精神科デイケアなど多角的なアプローチにより、患者さんのお悩みの相談から社会参加までトータルなサポートを実践しています。今回は、「精神科医として患者さんの社会参加をサポートすることで、地域に貢献したい」と語る同クリニックの理事長・院長である西江雅彦先生に、開院の背景をはじめ、地域の特性やクリニックの特徴、今後の展望などについてお話を伺いました。
施設紹介
■ 医療法人 西江こころのクリニック
福岡県春日市春日原北町4丁目11
メディカルシティ春日原3F
西江 雅彦 先生
(医療法人 西江こころのクリニック 理事長・院長)

母の死をきっかけに、経営者から医師に転向

西江 雅彦 先生
(西江こころのクリニック 理事長・院長)
私は大学に進学するにあたり、医学部に進むかどうか悩んでいましたが、結局医師過剰時代を見据えて医師になる道は選ばず、経営学・経済学を学びました。大学在学中には学習塾も経営し、それなりに軌道に乗せることもできました。
ところが資格試験の勉強を始めようとした矢先、人工透析を続けていた母がくも膜下出血で倒れてしまいました。母の入院した病院では、親身になって対応してくれた医師や看護師ももちろんいましたが、母の最期を看取ってくれた医師から心ない対応を受け、大きな憤りと悔しさを感じました。この経験をきっかけに、「患者さんとご家族に寄り添える医師になりたい」という思いが生じ、医師を志すことを決めました。
医学の道に進むにあたっては、将来は私の地元である福岡県で開業して地域に貢献したいという思いから、産業医科大学に進学しました。またその頃、日本でもメンタルクリニックの需要が増加していたことから、精神科を専攻しようと決めていました。
大学卒業後は、わが国で初めて精神科デイケアの承認を得た福間病院をはじめ、福岡県内の3つの病院で診療経験を重ね、2008(平成20)年4月に開院に至りました。
福岡市のベッドタウンで、家族ぐるみで診察
当院の位置する春日市は福岡市のベッドタウンとして発展した地域であることから、博多や天神に勤務されている働き世代の方やそのご家族が多く受診されます。なかには、子どもを含めた家族全員を診察しているような場合もあります。博多や天神にも行きやすいJR鹿児島本線と西鉄天神大牟田線の駅から徒歩数分という、利便性の高いメディカルビルの3階なので、仕事帰りに受診される患者さんも比較的多いです。
メディカルビルにあることで、患者さんは人の目を気にせずに受診できるだけでなく、同じビル内にある内科や皮膚科、歯科のクリニックにもまとめて受診できるというメリットがあります。
広範囲の精神疾患を診察
~児童・思春期・不登校外来で子どもの精神疾患にも対応~
当院では、医師が非常勤を含め6名(常勤3名、非常勤3名)在籍しています。常勤医3名のうち、私と副院長は日本精神神経学会の精神科専門医として認知症を含む精神疾患全般の診療を担当し、もう1人の常勤医は児童・思春期・不登校外来を担当しています。3名の医師がそれぞれの専門性をもって診療にあたっているため、広範囲の精神疾患を診察することができます。特に児童・思春期・不登校外来は、当院近辺に小児の精神疾患を診療しているクリニックが少ないためニーズが高く、日々多くの患者さんが受診されています。
一般の精神科外来と児童・思春期・不登校外来は、玄関から完全に分けました。これも、子どもの患者さんやそのご家族が他の人の目を気にせずに受診できるようにするための工夫です。

児童・思春期・不登校外来の玄関(写真左手前)。
一般の精神科外来の玄関(写真右奥)と完全に分かれている。
患者さんが快適に過ごせるような工夫を凝らす
開業するにあたり、患者さんが待ち時間を快適に過ごせるよう、院内設備の工夫を凝らしました。待合室には特にこだわり、各ソファーの間に特注のパーテーションを設置することで、患者さん同士が視線を合わせずにすむようにしました。パーテーションで隔てられたブースは全部で10個あり、合計で約20名が座れます。患者さんが通院を重ねるうちに知り合いができて、時には待合室がパーテーションを越えた語らいの場になることもありますが、特に初めて来院される患者さんには「パーテーションがあって助かった」と言ってくださる方も多く、好評です。パーテーションがあることで周囲の目を気にせず眠ることもできますし、ソファーの下に設置したコンセントでパソコンやスマートフォンの充電も可能です。待ち時間が長くなってしまってもリラックスしてお待ちいただけるのではないでしょうか。
そのほか、院内は段差のない完全バリアフリー設計にし、トイレも広めにして床レールのない吊り戸にしました。このことで高齢患者さんが車いすや杖で引っかかるような懸念が低減します。

待合室。背の高いパーテーションで隔てられたブース内で、患者さんはリラックスして待つことができる。

トイレ。広めかつバリアフリーに設計したことで、
高齢者や車いすの患者さんも安心して利用可能。
多職種による立体的な視点から患者さんをサポート
当院の理念は、薬物療法に加え、認知行動療法/カウンセリング、訪問看護、精神科デイケアを導入し、「立体的な診療」を提供することです。この理念を実践すべく、当院には医師、看護師、臨床心理士/公認心理師、心理カウンセラー、精神保健福祉士、社会福祉士、医療事務といった総勢約30名の医療スタッフが在籍し、「多職種によるチーム医療」を実践しています。以下に、個々の取り組みについてご紹介します。
-
認知行動療法/カウンセリング
臨床心理士と心理カウンセラー各2名が、臨床心理士は主に患者さんの自己分析・自己理解を通じて自己肯定感を上げる認知行動療法を、心理カウンセラーは主に患者さんの悩みを聞きアドバイスするカウンセリングを行っています。ただ、患者さんのお困り事が性別ならではのものの場合は、患者さんと同性のスタッフがお話を聞くなど、患者さんの背景や悩みに応じて柔軟に担当を調整しています。
-
訪問看護
看護師と精神保健福祉士各1名がペアとなって訪問看護にあたることを基本としています。訪問看護を行うことで、患者さんの自宅での過ごし方や部屋の状態、ご家族の意見など、クリニックでの診察では見えなかった側面を把握することができ、患者さんを立体的な視点から支援することができます。訪問看護の結果カウンセリングが必要と判断された場合は、次回の訪問看護には臨床心理士も同行するなど、適宜必要なスタッフが加わることができるのも、多職種が在席している当院ならではの強みといえます。
-
精神科デイケア
3時間のプログラムを1つの単位とした精神科デイケアを行い、社会参加に向けて心身を整えてもらいます。プログラムの内容は多岐にわたり、認知行動療法を通じてストレスへの対処法を体系的に学ぶ「ストレスコントロール」、体幹を鍛えたりストレッチによるリラックス方法を学んだりする「リラクゼーションストレッチ」、ゲームを楽しみながら人とのコミュニケーション力を身につける「レクリエーション」のほか、ピラティス、映画鑑賞、生け花、陶芸、料理などの趣味講座的なプログラムも揃っています。これらのプログラムは、外部講師に頼ることなく、当院の看護師や精神保健福祉士、事務長、心理カウンセラーなどのスタッフが主体的に取り組んでくれています。
リワークプログラムで復職支援
~「5つの能力」が身についているかどうかで復職可能性を判断〜
当院の精神科デイケアはリワークプログラムも兼ねており、患者さんの復職支援にも積極的に取り組んでいます。以前は、症状が改善したか否かが復職可能かどうかの判断基準でしたが、最近は、①就職意欲力、②生活リズム力、③疲労回復力、④通勤力、⑤職場適応力の5つの能力が身についている必要があるという考え方があります。そこで精神科デイケアを模擬職場にみたて、月曜から金曜まで毎日通っていただきます。それにより、患者さんの疲労回復力や通勤力を評価できるほか、生活リズム力や職場適応力を身につけることができます。当院の精神科デイケアを通じて復職できた方が多数いらっしゃる一方、うまくいかなかった場合もあります。そのようなときは、理事長が顧問を務める福岡障害者職業センターに紹介するなど、地域の復職支援プログラムと連携して更なる復職支援を行います。
各職域にリーダーを配置し、良好なチームワークを維持
当院はスタッフ数約30名とクリニックとしては大所帯なため、職種ごとにリーダーを配置して良好なチームワークの維持に努めています。リーダーは職種ごとにスタッフの状態を把握し、週1回のリーダーミーティングにて全リーダーで共有しています。加えて、全スタッフが参加する全体ミーティングも毎週月曜日の朝に行っており、スタッフ間の定期的な情報共有を徹底しています。これによりスタッフが互いに連携して患者さんをフォローすることができ、また、互いに気兼ねなく休暇を取得でき、生活の質を向上させることができます。
スタッフ教育では、主に副院長と看護師長が問診のしかたや患者さんに対する接し方など、細かな点まで指導しています。また治療薬に関する勉強会には全スタッフに参加してもらっています。これにより医療事務であっても治療薬の名称と薬効を把握できるので、患者さんから問い合わせの電話があった場合にも、適切に他のスタッフに内容を伝えることができます。
地域の病院・クリニックと、互いに高め合う関係を構築
私は地域の精神科非専門医の先生に向けて講演する機会をいただくことがあります。その際、非専門医の先生が処方することのある、睡眠薬や抗不安薬などの精神疾患治療薬の適正な使い方について、特にお伝えするようにしています。もしそうした薬剤の使用方法についてお困りの場合は、当院にご紹介いただくようにお願いしています。患者さんをご紹介いただくということは、逆に当院から患者さんをご紹介するきっかけにもなり、結果、患者さんを介した連携を構築することにつながります。このような連携関係は、ただ患者さんを紹介し合うだけでなく、お互いに知識を共有して高め合う、地域医療において好ましい状況ではないかと思います。
診察前に精神保健福祉士や
看護師が患者さんの話を聞いて緊張をほぐす
初診の患者さんが来院された際は、まず精神保健福祉士が1時間以上かけて問診し、病歴や症状等についてしっかりお話を伺います。患者さんはそれだけで十分話をすることができたと感じ、診察する頃にはすっかりリラックスされていることも多くあります。ただ初診の場合は、問診に加えて診察にも1時間程度かかるため、患者さんに負担を強いることになります。そこで最近は、問診を行った後は一度お帰りいただき、日を改めて診察するような取り組みもしています。また、再診の前には必ず看護師が患者さんにお話を伺い、様子を確認するとともに患者さんの緊張を和らげるようにしています。
精神保健福祉士や看護師が聞き取った情報はカルテに記載され、スタッフ全員に共有されます。医師はその内容から患者さんの状態を事前に把握できるので、スムーズに診察を始めることができます。
薬剤変更成功のカギは患者さんとの良好な信頼関係
精神科の薬物治療において重要なポイントは、副作用をしっかりコントロールして効果と安全性のバランスを高めることだと考えています。そのため長年にわたり使用してきた薬剤であっても、より副作用の少ない薬剤が登場した際は積極的に切り替えています。患者さんは使い慣れた薬剤を切り替えることに不安を感じやすいので、しっかり患者さんとの信頼関係を構築しておくことが非常に重要です。「この先生が言うなら変えてみよう」と思ってもらえるような関係性ができていれば、大きな不安を感じることなく薬剤変更に応じてもらえるのではないでしょうか。このような良好な信頼関係を築くためにも、ホスピタリティの精神をもって患者さんに接することを肝に銘じながら、日々診療にあたっています。
今後
の
展望
継続的に地域に貢献できる
医療の提供を目指したい
地域の方々の健康のため、これまで積み上げてきた当院の医療を地域の方々に提供し続けるべく、次の世代の人材をしっかりと育てなくてはいけないと考えています。また、患者さんにとって通院の利便性の高い場所に小規模かつ専門性の高いクリニックを配置するような、医療グループを展開する構想ももっています。これにより地域の方々がより通いやすく、かつ質の高い医療を受けることが可能になるのではないかと考えています。実現できるかどうか分かりませんが、より良い医療の提供を目指して、これからも尽力していきたいと思います。

- vol.01 医療法人しもでメンタルクリニック
- vol.02 医療法人ウェルライフ アイさくらクリニック
- vol.03 医療法人眠りとこころのYOUクリニック 有吉祐睡眠クリニック
- vol.04 医療法人聖心会 清水クリニック
- vol.05 医療法人 円山公園メンタルクリニック
- vol.06 あかりクリニック
- vol.07 木村こころのクリニック
- vol.09 医療法人啓光会 HIKARI CLINIC
- vol.10 医療法人社団つたの葉 古新町こころの診療所
- vol.11 医療法人社団聖眞会 きしろメンタルクリニック
- vol.12 ただしメンタルクリニック
- クリニック訪問記インデックスへ戻る
